日中の陽射しは肌を焼き付け、確かに夏の到来を感じさせますが、陽が落ちれば中秋を思
わせるように気温が下がり、爽やかな風が家の中を巡ります。心地良さの中にも、梅雨ま
近のこの時期とは何か違う不思議な感覚もあって、あれ程過ごしにくいと嫌っていた、べ
たーっと纏わりつくような梅雨の肌感覚が、ほんの少し懐かしくもあります。
さて、昨今公用書はさておき、私信さえも手書きからパソコンへと移りつつあるようです
が、変換されるままにとんでもない漢字が使われていることも珍しくありません。パソコ
ンに依存するうちに、読めるけれど書けない漢字が増え、まして送り仮名への意識は希薄
となるでしょう。
月々の詠草の送り仮名のふり方に苦言を呈し、新青虹五月号へと寄せられた水本編集長の
文章には、広辞苑とても曖昧だと書かれています。活用に際して全く変化をしない語幹を
表示しながら、その活用は徹底していないとの事。詠草の清書にあたり、何の疑いもなく
広辞苑の表記に従っていましたが、心せねばなりません。そうは言っても歌の場合、作者
の意図により敢えて不要な文字を、視覚的な強意として付け加える場合もあり、やはり正
解はないようです。
『五月号誌上より』
・海苔加工つぎし夫婦の息合ひて伊勢海苔の角黒々と張る(金丸満智子)
・清水湧く土地のあるらし里山の低きも絶えぬ小流れありき(井口慎子)
・攻めらるる外つ国遠くへだたりて幼の涙拭くすべもなし(中川りゅう)
・長風呂に創を癒して気ままなる湯浴みたのしむ春立つ日にも(山本浩子)
・かじかみし手に息かけて戸を開く東の空に茜雲みゆ(後藤まゆみ)
・家々の灯りに添へて明るめる梅と暮れゆく里のやさしき(中世古悦子)
・蟹紅く煮られ食はるる湯の宿に着くも帰るも雪のうちなり(水本協一)
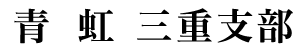
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。